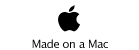卒業生の卒業研究と進路
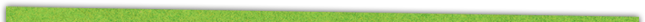


1. 1990年度卒業生
前田 典子 「先端技術産業と環境問題-半導体産業と地下水汚染」(商業)
大屋 和隆 「祖先崇拝の変容」 (電機メーカー)
柳 砂由美 「高齢化社会と住まい-高齢期の住まい方-」 (福祉サービス)
柳澤 紀子 「階層に関する一考察」 (出版社)
籔 克彦 「日本人における価値意識と社会意識の変容」 (出版社)
2. 1991年度卒業生<在外研究のため、卒業研究指導は蔵持先生>
浦川 政治 「コミュニケーション・ギャップを越えて」 (テレビ局)
工藤 亮子 「現代の『こどな』たち」 (出版社)
白水 朗 「M字型就労パターンにみる女性労働」 (銀行)
鈴木 哲朗 「非行論」 (高校教員)
3. 1992年度卒業生
細貝 和 「我が国におけるリゾート開発の現状と問題点」 (デザインスタジオ・ディレクター)
坂口 久乃 「医師-患者関係の社会学」 (出版社)
4. 1993年度卒業生
芝田 光正 「日本の林業と山村振興」 (福祉施設)
村田 久 「地域イメージの形成プロセス」 (大学教員 目白大学教授)
5. 1994年度卒業生
大城 修一 「『公害問題』の再考察」 (教職員共済)
6. 1995年度卒業生
高田 健二 「戦略としてのボランティア」 (国際協力機関・社会活動家・手品師)
黒澤 悦子 「TRAVAIL・働く女性の現状」 (地方公務員)
齋藤 未来 「『豊かさ』と余暇の社会学」 (アミューズメント産業)
清水石 珠実「政治家の『顔』の社会学的研究」 (ジャーナリスト、Nikkei N,Y, 在ニューヨーク)
西内 孝至 「埼玉県の交通網形成についての一考察」 (地方公務員)
平田 潤 「地域経済の活路を拓く」 (新聞社)
三田村 義崇「日本における中小企業の経営者像に関する一研究」 (会社経営)
水上 貴一朗「東京の都市計画とその思想」 (情報機器産業)
矢崎 みゆき「花は幸せを感じるか」 (教育サービス)
7. 1996年度卒業生
肥塚優一 「阪神・淡路大震災の被災状況及び復興計画に関する一考察」(生命保険)
佐藤真也 「音楽の意味論」(バークレー音楽院修了、ジャズピアニスト、ピアノ教室主宰)
高浦優子 「高齢者介護における家族の役割」(地方公務員)
高橋陽子 「後期イスラーム時代の中東におけるカフワ普及の諸相」(人研大学院を経て、研究機関)
平田浩哉 「川をめぐる人間と自然」(出版社)
丸山和子 「アイヌの自然観」(福祉施設)
横山俊太郎 「遷都論」(住宅関係)
8. 1997年度卒業生(98年度前期卒業者を含む)
池田奈津美 「アニマル・セラピー」(福祉施設)
杉本昌志 「デジタル世代のメディアコミュニケーション考」(FM東京)
瀬尾尚史 「マレーシアにおける人の移動」(コンサルタント)
広岡歩 「ジャック・リヴェット論」 (執筆・編集者)
吉田英樹 「ゴミ問題とリサイクル」(金融)
9. 1998年度卒業生<在外研究のため、卒業研究指導は蔵持先生>
佐藤有美 「健康食品」(食品産業)
西山わか奈 「エスニックコミュニティと共生」(国際協力機構、在エチオピア)
10.1999年度卒業生
相澤康之 「アジア諸国における共同体の確立の可能性について」(長瀬産業・サステナビリティ推進室)
松岡史江 「音楽の歴史」(家事手伝い)
11.2000年度卒業生
坂田奈菜子 「ゴミ問題--意識改革への挑戦--」(SPIRALS 編集者)
村岡素子 「近現代日本女性史のなかの巫女」(都公務員)
七尾典子 「首都圏在住の日本人ムスリムに関する調査研究」(社会調査機関)
小見山秀雄 「所沢の歴史と織物産業」(福祉産業)
阿部敏之 「尾道論」(ヨーロッパ放浪予定)
星谷知美 「沖縄の墓制・葬制」(自営業)
道広雅典 「武士道における切腹の意味について」(金融・保険)
国分かおり 「日本の英語教育と国際化」(通訳・語学教育)
12.2001年度卒業生
輿水淳一 「ユダヤ人のアイデンティティ」(東進ハイスクール講師)
木全祐一郎 「発想支援システムの構築についての考察」(製造業)
堀真純 「ビルマの人権侵害と軍事政権」(英国大学院、進学)
秋山香織 「少年の万引きに関する一考察」(外食産業)
橋本綾子 「東南アジア少数首狩り民族の死と再生の儀礼」(イラストレーター)
山形人士 「インターネット上の音楽配信サイトに関する研究」(システム・エンジニア)
辻中愛美 「少子高齢化社会の福祉と経済」(システム・エンジニア)
松本勝秀 「介護保険と介護の社会化」
13.2002年度卒業生
加藤健司 「雇用のミスマッチに関する一考察」 (情報産業)
八木美帆 「『あいだ』の思想 -黒川紀章、島田雅彦を通して現代を見る-」(専業主婦)
横尾俊成 「『アメリカ人』のアイデンティティ-戦争とアメリカ、アメリカ人-」
(元・港区区会議員、慶応大学非常勤研究員)
李 義炯 「日本の年金制度に関する研究」(商業)
笠嶌 梨乃 「ファストフードからスローフードへ」(金融)
14.2003年度卒業生
池端 宏之 「近現代日本のスポーツとスポーツ振興」(人研大学院を経て、研究所職員)
小田中 幸代 「美輪明宏にみる現代社会」
金井 絵里 「中古リサイクルビジネス論」 (情報産業)
北爪 秀紀 「情報戦と世論形成」 (人研大学院を経て、ウェブデザイン会社経営)
今野 多恵子 「移動体メディアの受容と変容」(情報産業)
市東 貞人 「比喩表現における各国文学の比較研究」 (システム・エンジニア)
松下 憲一 「ギャンブル産業の社会的存在価値」 (出版社)
山田 美保子 「観光産業におけるエコツーリズムの役割」 (ツアー産業)
荒木 泰成 「ジェンダー意識の国際比較研究」
田中 美弥 「二.二八事件と台湾の独立」
15.2004年度卒業生
岩本 理恵子 「日本における働き方・働く意識の変化」(情報産業)
遠藤 麻衣子 「国際結婚からみる日本の国際化」(出版関係)
小野 恵 「脱臭する日本人」(警備安全管理産業)
木之下 ゆり子 「韓国映画による異文化理解」(メディア産業・動画配信サービス)
小宮山 恵 「人間とペットの共生社会」(クレジット産業)
城 美穂 「広島県呉市における平和学習」(航空産業)
藤上 和穂 「大学生の学習意欲における気分一致効果」(商社)
村尾 梨乃 「日本における香りと癒し」(商社関係)
16.2005年度卒業生
秋田 まどか 「現代社会における若者の労働観」(情報産業)
安藤 由紀 「武者小路実篤の理想郷『新しき村』の現代における意義」
池山 由希子 「日本における国際ボランティアの現状」
内山 幸洋 「『時間』と日本人」(専門商社)
北島 淳平 「真田三代の真相」(商社)
幸村 瑠美香 「マレーシアにおけるブミプトラ政策の成立と展開」
佐々木 彩乃 「ひとと音楽」(インターネット産業)
寺輪 潤一 「子供観の変容と家族の現状」(塾経営)
平井 孝幸 「多民族国家シンガポールで知る言語の役割」(資源産業)
山田 雅大 「現代における日本人の海外移住と移住斡旋」(住宅産業)
若生 亜里 「タイ王国のマーケットにおける人々の消費力」(ファッション産業)
根岸 昇平 「アジア太平洋国家としてのオーストラリアの可能性」(住宅総合産業、在バングラデシュ)
17.2006年度卒業生
小澤 祐季 「女性の就業意識と結婚観」(空調機器メーカー)
上田 めぐみ「世界における日本のアニメ」(芸能事務所マネージャー)
18.2007年度卒業生
浅田 裕紀 21世紀の日韓交流 (結婚産業)
池田 遙子 日本の経済格差の現状と今後 (宗教機関)
石田 純一 アジア的ラグビーの在り方 (私鉄)
内田 慶 アジア諸国の対日感情 (建設会社 ゼネコン)
小林 靖明 日本サッカー界に学ぶ日本ラグビーの在り方 (エネルギー産業)
瀬尾 貴則 写真論 (商社)
冨田 卓志 岐阜県における方言の未来 (地方銀行)
冨永 芳行 ペットと人間・共生への道 (県議)
中山 朋子 日本映画にみる死生観 (システム産業)
藤田 逸人 マレーシア経済におけるイスラム金融 (商社)
常藤 郁子 アジアにおける刺青文化と女性観 (旅行産業)
森 啓 地方移住の動向と政策課題 (人材サービス産業)
19.2008年度卒業生
伊倉 佑哉 アジアにおけるサッカーの発展とボーダーレス化(地方公務員)
掛井 雄馬 日本の総合格闘技 (生命保険)
成田 謙介 笑いの教科書・試論 (情報産業)
尾畑 知洋 人口減少社会における外国人政策 (社会奉仕団体)
朝枝 恵梨 地球温暖化問題における東南アジアの重要性 (商社)
氏田 美子 フェアトレードの現在と未来 (損保)
古賀 千賀子 紛争ダイヤモンドの国際史 (専業主婦)
白井 克尚 東京における公と民のパートナーシップ (地方公務員)
手塚 智之 日本におけるムスリム団体の形成と活動 (大学職員)
名畑 友晴 中国における知的財産権の現状と将来展望 (建設産業)
牧原 麻香 イスラム金融の発展と日本 (電機産業)
森 惇志 放送メディアの未来形 (放送局)
森本 友貴 食生活と人間 (情報産業)
林 幸司 日本プロ野球チームの運営と地域社会 (税理士事務所経営)
山縣 敦 滞日インド亜大陸出身者の移住過程 (LEC会計大学院 兼任講師)
山田 瑛子 地域開発と世界遺産 (損保)
20.2009年度卒業生
萩原 悠太 台湾の若者世代における今後の台湾語の展望(不動産業)
大浦 蒔絵 国境を越え結ばれる世界(ブライダル産業)
市岡 祐次郎 「ワタシ」を着る人(写真家)
川野 絵美子 ワークライフバランス(IT産業)
菊池 貴之 マンガにみる女性の魅力と理想像
河野 有紀 地域活性化と商店街
佐藤 茉里 日本における食育の可能性(商社)
島本 佳奈 映画でみる昭和(IT産業)
山﨑 祥子 広がるイスラム金融(生命保険)
-
21. 2010年度卒業生
豊田修平 ユダヤ人ネットワークと経済 (建設、ゼネコン)
望月春香 裁判員制度の導入と量刑に関する考察(製造業)
増澤諒 近年における大学生の就職活動とその問題点(研究者)
山本純子 現状から見る「婚活」予備軍の未来 (IT産業)
石原遼一 サッカーと社会 (出版社)
貝田雅尭 日本サッカー界におけるダービーマッチの現状と将来構想 (私鉄)
井出勝也 二次元キャラクターの「神格化」(専門商社)
榎本誠 日本の音楽の普及と「タイアップ」(製造業)
山田峻介 人気アイドルからみる熱狂システムづくりのメカニズム (企画)
中山純輝 日本における緑茶飲料の未来 (商社)
榎本梨絵 日韓両国における食文化の相互受容 (公務員)
山田沙織 現代中国における貧困層の実態 (銀行)
22.2011年度卒業生
川嶋 久人 戦後ハンセン病史 (中国留学を経て、写真家)
宇佐見 浩紀 天皇制における女系への皇位継承(IT産業)
川口 卓也 日本における真珠産業の展望(人研大学院を経てコンサルタント企業)
河添 結日 限界集落における活性化の意義と地域課題(通信社)
中村 浩之 在日イラン人の暮らし向き(薬品業界)
西村 章吾 ラジオの生き残り戦略(IT産業)
吉田 優美 日本における皆婚社会の崩壊と婚活現象(生命保険)
23.2012年度卒業生
阿部 柚子 ラオスにおける衛生教育の意義と今後のあり方 (教育産業)
尾花 政和* キャラクターと地域・産業振興に関する考察
新保 拓将* Jリーグの観客動員数の現状と課題
難波 亮太 ライブマナーの現状と課題 (住宅産業)
原田 政弥 「家電」の文化的創造力 (流通産業)
* 2013年度卒業(ただし、卒業研究は2012年度提出)
24.2013年度卒業生
高橋 耕平 タイ南部におけるイスラム教徒と仏教の衝突について(商社)
田島 健大 中世アジアにおける我が国との文化的交流(機械)
中里 幸裕 現代の占星術
池田 梓 韓国労働市場における男女格差の今後のあり方(IT産業)
伊藤 嵩明 日本におけるグラフィティ文化 (機器メーカー)
伊部 健史郎 北陸本線における第3セクター鉄道の課題と構想(鉄道)
長田 剛 「アラブの春」のイスラエルへの影響(大手コンビニ)
キアラシ ダーウッド ハラール認証をめぐる動向と日本のハラール市場(証券)
金 秋池 孔子文化の観光開発(進学予定)
古里 唯 「夢の」海外移住に関する考察(IT教育)
山本 利樹 「オリンピック競技としての相撲」に関する考察(IT産業)
25.2014年度卒業生
成井 龍之祐 東南アジア社会のジェンダー (放送)
番匠 ジュリア柚衣 日中韓における漢字使用と文字の発展(企画)
吉田 有輝 競技スポーツにおける指導力と競技成績 (銀行)
26.2015年度卒業生
山本 祥寛 ハラール食品マーケットの現状と課題 (IT産業)
赤間 大樹 日本におけるイスラム金融の現状と課題(地方公務員)
麻生 里奈 イラクの「平和」(他大大学院をへて、出版社)
植竹 祥太郎 道徳の教科化から考える日本の道徳教育(公共団体)
小池 寿裕 東南アジア諸国の開発と発展(人研大学院をへて、IT産業)
坂本 智行 赤羽地域研究(建設産業)
西 雅彦 日本の難民受け入れ政策の現状と課題(商社)
浅井 祐花 若者のボランティア観(生活科学産業)
石井 諒 日本文化の対外輸出(不動産業)
大内 薫 滞日ムスリム留学生の意識調査(IT産業)
小林 暖乃 オリンピック・レガシー論(食品産業)
中西 恭輔 日本における外国人労働者の実態(情報産業)
中村 聡 東南アジアにおけるサッカー発展の可能性(IT産業)
光永 亮太 家族問題といじめ(教育)
渡邉 彩加 日本におけるハラール認証制度(通信産業)
27.2016年度卒業生
植木 貴大 東南アジアにおけるサッカーとその海外展開 (クレジット産業)
ゴ インシ 中国における教育格差 (人研大学院を経て中国にて就職)
斉藤 央 日本における技能実習生の現状と課題 (商社)
澤井 日奈子 海外和食料理人の技術習得と和食の未来(食品)
田中 由香 中国における対日感情の実態と悪化要因(早稲田大学大学院予定)
西 優 戦前日本の安全保障の理念と敗因(造船)
本橋 大希 アジア社会におけるテレビ報道 (情報産業)
山口 拓也 在日ムスリムの教育問題 (旅行産業)
28.2017年度卒業生
石川 拳太朗 多文化共生社会と移民に対する日本型社会統合政策の模索 (報道)
今関 悠 アジアにおけるスポーツの発展と民族性 (IT産業) (2018年9月卒業)
笠原 遊 アジアにおける社会開発 (食品産業)
酒井 足日 これからのラジオ (広告)
清水 佳織 選択理論心理学による人間関係の改善 (コンサルタント産業)
英 佳那 居住地移動に伴う関西方言の変化 (報道)
八田 冠奈 インドネシア在住の日本人妻に関する考察 (在インドネシア)
松井 怜蒔 アジアの英語教育 (2018年9月卒業) (IT産業)
29.2018年度卒業生
高橋 朋玄 日本とブラジルの野球交流の歴史 (石油産業)
福井 和輝 日本IT産業における人材活用の構造と外国人雇用の影響 (IT産業)
古橋 拓朗 フィンランド教育の成功要因に関する考察 (金融)
保坂 良 日本における組織ジャーナリズムの構造的欠陥 (金融)
松永 裕樹 観光まちづくりの課題と解決案 (IT産業)
清水 雄斗 拡大するイスラーム金融 (資格試験に挑戦)
水谷 健吾 二分心からみるムハンマド (放送)
30.2019年度卒業生
豊田 絃 ヨーロッパにおけるロマ民族(IT産業)
長沼 孝輔 日本における音楽業界におけるガラパゴス化(商業)
奥ノ木 慶 サウジアラビアの脱石油化(不動産団体)
宮田 陸耶 世界仏教の課題と現状から見る日本仏教の発展(寺院)
萩原 成俊 在日ムスリムから見る各国のイスラーム文化比較(機械)
土生 真義 イスラム金融の現状と課題(コンサルタント)
矢部 修平 日越関係の歴史と展望(ファイナンス)
塚本 隆矢 日本国内の経済格差(生命保険)
三田 勇樹 ムスリムにとっての選択肢:日本(コンサルタント)
平山 朱音 日本のプロ野球ビジネスの現状と展望(スポーツ・IT)
山嵜 菜々子 観光の時代における宗教施設(金融)
平山 理襟 イスラム教徒の日本での生活と日本社会の対応(金融)
松村 匠馬 日本における外国人労働者について(広告産業 2021年度卒業)
以上、店田ゼミの学部卒業生の一覧です。
人数は、211名です。その他、ゼミと関わりのある卒業生を含めると、もう少し多いかも知れません。