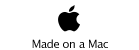UM調査(マラヤ大学調査)
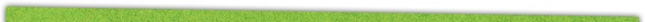


1997年
第1回目のマラヤ大学学生調査を行いました。
相澤康之、佐藤有美、西山わか奈、松岡史江の4名および大学院生の入江正勝と 村田久の2名と少数精鋭です。
1997年10月29日から11月04日にかけてマラヤ大学キャンパスにおい て、マラヤ大学学生を対象者として生活の実態と意識を調査しました。回答者は42名でした。 質問ガイドラインを使用し、社会的属性項目のほかに、49の質問項目について回答してもらいました。内容は、学業、ファッション、遊び、食、文化、日本認識など多岐 にわたります。
1998年3月には、第1次報告書として、英文報告書 Preliminary Report of Social Survey on Lifestyle of UM (University of Malaya) Students in Kuala Lumpur, Malaysia を刊行しました。
1998年
教員の在外研究(エジプト)のため、実施せず。
1999年
第2回目のマラヤ大学学生調査を行いました。
坂田奈菜子、村岡素子、七尾典子、小見山秀雄、阿部敏之、星谷知美、道広雅典、国分かおり、 輿水淳一、木全祐一郎の10名、および大学院生の村田久、総計11名です。
フィールドワークの対象地は、東南アジアのマレーシア・クアラルンプルです。
今回は、1999.11.04~11.10にかけてマラヤ大学キャンパスにおいて、マラヤ大学学生を対象者として家族と世帯の実態と意識を調査しました。回答者は124名でした。
2000年7月には、第1次報告書として、英文報告書 Preliminary Results of Social Survey on Family and Household of UM (University of Malaya) Students in Kuala Lumpur, Malaysia を刊行しました。
宿舎は、森の中の一軒家、大学教員の家族用の大きな家でした。これを男性用、女性用と2軒を借りました。
2000年
第3回目のマラヤ大学調査を行いました。
今回は、店田ゼミの学生だけでなく、蔵持先生のゼミ生も一緒に調査を行いました。蔵持先生が在外研究中ということだったと思いますが、店田ゼミに参加しました。
参加者は、山形人士、土田隆、秋山香織、大沢智子、田村陽子、橋本綾子、堀真澄、河村亜紀、大学院生の村田久、4年生の木全祐一郎です。
今回は、2000.11.04~11.09にかけてマラヤ大学キャンパスにおいて、マラヤ大学学生を対象者として結婚に関する意識を調査しました。回答者は205名でした。
2001年6月には、第1次報告書として、英文報告書 Marriage Survey of UM (University of Malaya) Students in Kuala Lumpur 2000 を刊行しました。
2001年
この年の調査は、いわゆる9.11の大きな影響を受けた。当初予定した学生参加が大幅に減って、3年生3名、院生一名、助手一名、教員一名の僅か6人の調査実施となった。調査は、2003年の11月8日から13日にかけて実施した。もとより、不穏な空気や危険な状況に遭遇することもなく、きわめて順調に調査は終了した。
有効回答者数は、125名のマラヤ大学学生であり、通常年度の調査に比べると、半分以下の数であった。報告書は、Gender Survey of UM Students in Kuala Lumpur 2001, Waseda University, July, 2002. として、刊行されている。
2002年
本年度の調査は、ジェンダーとセクシュアリティに関する意識調査である。マラヤ大学学生を対象として、2002年10月31日より11月5日までの日程でマラヤ大学キャンパスにおいて実施された。参加者は、3年生5人、4年生3人、院生2人、教員一名であった。
今回の調査では、ジェンダーおよびセクシュアリティに関する実態と意識の調査を行ない、280名のマラヤ大学学生から有効回答をうることができた。今回の調査に当たっても、インドネシアのバリ島でのテロ事件をうけて、現地調査の安全性を危惧する声もあったが、調査は大学キャンパス内であり、まったく支障なく調査を完了した。
今年で、5回目の調査となり、例年通り、協力者のマラヤ大学タン教授による、講演会とその後の交流会を始め、地域活動にもボランティア参加するなど、学生にとっては、マレーシアの学生との交流のみならず、ひろく庶民の人たちの生活にも触れる機会を得て、演習の成果のみならず、幅広い交流を実現できたことは有意義であった。
報告書は、2003年7月に刊行されている。Gender and Sexuality Survey of UM Students in Kuala Lumpur 2002, Waseda University, July 2003.
2003年
本年度の調査は、国家と人種(エスニシティ)に関する調査として、2003年11月12日から18日までマラヤ大学キャンパスにおいて実施された。対象者は、マラヤ大学学生である。有効回収数は、218名。男女比は、48.6%、51.4%であった。
今回の調査は、一時実施が危ぶまれたこともあった。というのは、昨年度まで協力者であったマラヤ大学タン教授が、5月に事故で急死したからである。しかし、その後、彼女の同僚教員たちの協力が得られることになり、予定通り計画は実施された。今年で、6回目の調査となり、例年通り、講演会とその後の交流会を開催し、マラヤ大学教員や学生も参加して、種族(エスニシティ)意識に関する報告をうけた。今年は、マラヤ大学が、昨年実施したアンケート調査の結果をもとに、「Social and academic interactions amongst UM students」と題する講演が行われた。我々の調査テーマにも直接的に関連するものであり、現地での関心テーマでもあることを改めて確認した。
2004年
本年度の調査は、2004年9月2日から9日まで、マレーシアの首都クアラルンプルにある、マラヤ大学キャンパスにおいて実施した。今年の調査は、結婚と出生に関する意識調査であった。調査参加者は、ゼミ三年生10名、院生4名、助手2名、教員1名の総勢17名であった。宿舎は、例年通り、マラヤ大学ゲストハウスで、2人一室の宿泊である。
有効回答者数は、317人、すべてマラヤ大学の学生である。男女比は、48.9%と51.1%である。うち、マレー系、51.7%、華人系、32.2%、インド系、12%、その他、4.1%となった。その他の調査結果の主なところを摘記すると次のようである。希望結婚年齢は、27.6歳、恋人のいる割合が、45.1%、希望する子ども数は、平均3.6人である。
2005年 結婚と出生に関する意識調査 9月7日から9月13日
2006年 若者文化に関する意識調査 8月23日から8月30日
2007年 ライフスタイルとエスニシティに関する意識調査 8月23日から8月30日
2008年 環境と生活に関する意識調査 8月28日から9月3日
2009年 文化とライフスタイルに関する意識調査 8月27日から9月2日
2010・11年
両年度は、教員の個人的事情により、UM調査は実施しなかった。ただし、2010年度については、学部生の作成した調査票を使用して、マラヤ大学教員によって、調査は実施された。その後、記入済み調査票は早稲田大学人間科学学術院まで郵送にて届けられた。ゼミ参加学生が、データ入力と集計分析を行って、調査報告書の作成を行っている。Multicultural Society Survey of UM students in Kuala Lumpur 2010 (Feb.2012)を刊行した。2011年度は、人科キャンパス内で早稲田大学学生の意識調査を実施した。
2012年
本年度のUM調査は、9月17日から9月21日まで、多文化社会における家族をテーマとして、Survey on Family in the Multi-Cultural Society of UM Students in Kuala Lumpur 2012 という表題の調査票を使用して実施した。参加者は、学部生14名、大学院生1名、教員等3名。有効回収数は、358票であった。報告書は、2013年5月に刊行した。
2013年
本年度の調査は、9月8日から9月13日まで実施した。参加者は、学部生9名、大学院生1名、教員等2名。Survey on Ethnicity and Religion of UM Students in Kuala Lumpur 2013 というテーマで調査を実施した。有効回収数は、355票。報告書は、2014年5月刊行した。
2014年
本年度の調査は、9月8日から9月12日まで実施した。参加者は、学部生10名、教員等2名。Survey on Ethnicity and Religion among UM Students in Kuala Lumpur 2014 というテーマで調査を実施した。有効回収数は、345票。報告書は、2015年に刊行。
2016年
ムスリムのファッションや日本イメージ、食に関する簡単なインタビュー調査を小規模に実施した。9月8日から10日までUMキャンパスで実施。参加者は、学部生2名、院生1名、教員等2名。